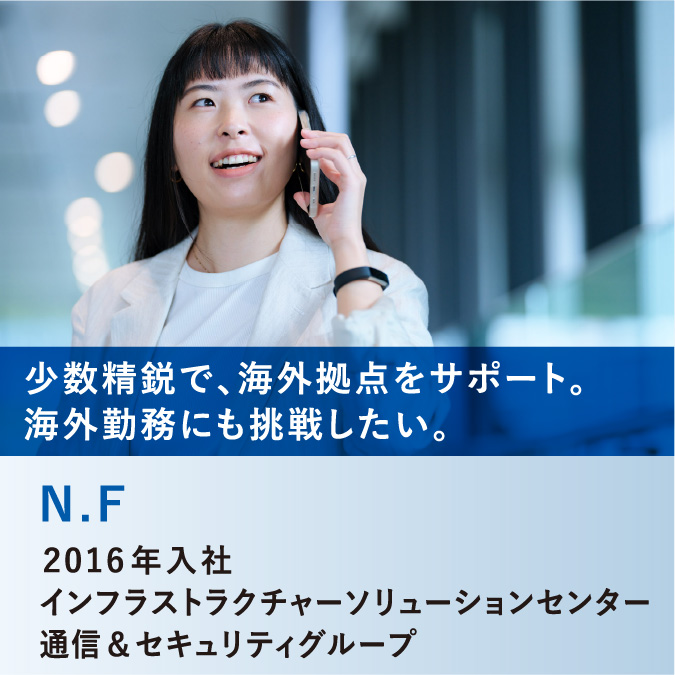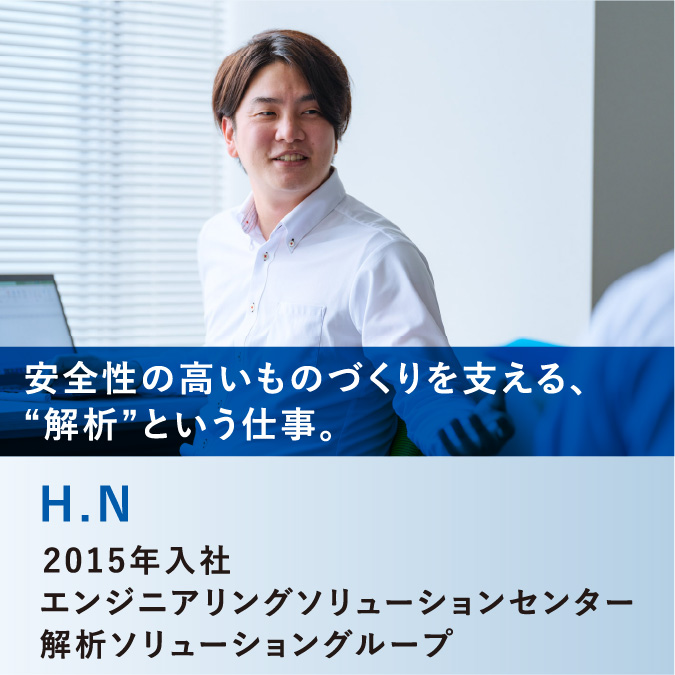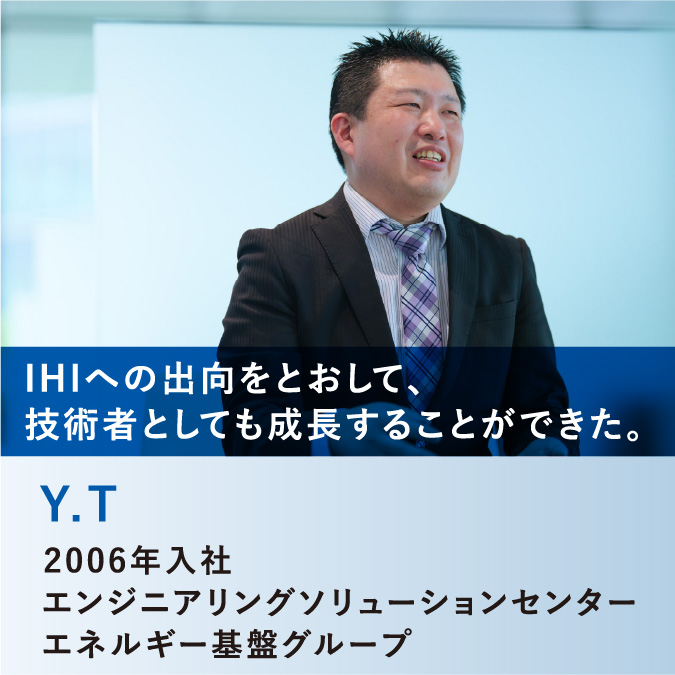H.N
2015年入社
サービスソリューションセンター 解析ソリューショングループ
H.N
2015年入社
サービスソリューションセンター 解析ソリューショングループ
- 2015年入社後、現部署に配属。航空エンジンの伝熱解析を任される。
- 2018年車両過給機の構造解析を担当。
- 2020年IHI航空・宇宙・防衛事業領域 民間エンジン事業部に出向。旅客機向けエンジンの維持設計を担当し、解析業務に加えて、設計業務にも携わる。
- 2022年IHIエスキューブ復帰。引き続き、旅客機向けエンジンの維持設計の解析業務に従事。
 入社の決め手は?
解析専門部隊がいる会社で
入社の決め手は?
解析専門部隊がいる会社で
責任ある仕事に携われる。

大学時代は、機械システム工学科に所属し、当時から“解析”に携わっていました。ゼミで「伝熱促進体の挿入による円管内熱伝達率特性」という研究テーマを選び、現象解明として解析を行なう中で、数値・視覚で現実の現象を把握していくことに楽しさ・面白さを知りました。
就職活動でも、解析に携わる仕事をしたいと考えていたところ、当社には解析を専門にしているチームがあることを知ったのが入社のきっかけです。特に航空エンジンの解析は、人命に直結する業務として責任感をともなう仕事です。ここなら、大学で学んだ知識を活かして解析の楽しさ・面白さを感じながら、かつ解析に関するエキスパート部隊がいるという環境で、自分自身の成長につなげることができるのではと思ったのです。その気持ちは、入社してから現在までまったく変わっていません。
 現在の仕事について
旅客機向け
現在の仕事について
旅客機向け
低圧タービン部品
解析・設計。
現在の仕事を細分化すると大きく2つの業務を専属で担当しています。エンジンの性能を維持向上させるための解析、もう一つが解析結果を将来の事例として整理するエンジンマニュアルの整備です。それらを正確に行なうためには、設計業務の専門知識・経験も必要になってきます。
2020年に、IHI民間エンジン事業部に出向した際に設計業務を担当し、ごくわずかな人にしか担当できないこうした業務を任されるようになりました。業務の中で責任の重さを実感する機会も多くありますね。

 仕事の面白いところは?
日々出会う難題に向かい
仕事の面白いところは?
日々出会う難題に向かい
自分が納得できるものを
出していく。
解析の仕事では、日々まったく違うケースに出会います。その中には、当然これまでにはないような事例も多くあります。解析結果が出ていたとしても、その結果の妥当性を保証するデータを集められなければ、予測の正確性が担保できない場合は、突き詰める必要があります。
過去の類似案件や解析結果の資料から、傾向が一致しているものを探し出していったり、時にはそれを組み合わせたり、非常に時間と労力が必要な業務でもあります。いかに、その難題を乗り越えるか。責任とプライドを持って自分が納得できる結果を出すことは、日々心がけていることです。
 印象に残っている仕事は?
ものづくりと
印象に残っている仕事は?
ものづくりと
解析業務への
理解度が深まった
IHI民間エンジン
事業部への出向。
IHI民間エンジン事業部に出向した際、工場で実物に触れる機会や、他で見たことない部品を見る経験などをさせてもらい、ものづくりの一連の流れを俯瞰して考えることができるようになりました。
それまで、解析はものづくりということをあまり実感していなかったのですが、いい意味で“全体のうちの一工程”であることを思い知り、改めて自分の業務を見つめるきっかけにもなりました。製造においてはすべてのセクションが全力で取り組むことで部品が完成します。そのことに対する理解が深まり、以来、自分もものづくりの一端を担い、パートナーから求められている仕事に対して120%の結果を出したい、と考えるようになりました。
また、出向をきっかけにものづくりの全体像が見えたことで、仕事の楽しさ・面白さ、そして責任感も一層深まったと感じています。

 今後の目標や会社の魅力は?
様々な
今後の目標や会社の魅力は?
様々な
エキスパートがいる環境で
成長することができる。
たとえば、解析業務をしている中で「ここに荷重がかかっているのに、なぜここに応力が発生するのか」といったような疑問点が出てくるケースがあります。そうした時に頼りになるのが、当社にいる様々な分野のエキスパートの方々。経験も豊富で、いつでも相談できる環境があるのは会社としての強みだと思います。
さらに、エキスパート集団なのでみんな仕事も早く、突然発生したイレギュラーなことにも対応力が非常に高い。こうしたエキスパートたちの仕事を間近で見ながら、自分自身もその中で成長することができるといったことは、当社ならではの魅力なのではないかと思います。
今後は私自身も、IHI民間エンジン事業部への出向で得た知識や経験を、社内に伝えていきたいと思っています。今の業務をほとんど一人で担当していることもあり、得た知識を伝えていくことで、ゆくゆくはチームをつくり、これまで以上にパートナーに頼られる存在を目指すことができたらと考えています。